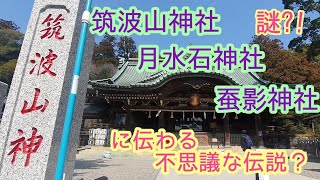筑波山神社|観光の魅力・歴史・アクセス方法・営業時間を写真&動画でチェック!
基本情報
- 名称
- 筑波山神社 (つくばさんじんじゃ)
- 所在地
- 〒300-4352 茨城県つくば市筑波1
- アクセス
- つくばエクスプレス「つくば駅」より筑波山シャトルバスで40分
JR常磐線「土浦駅」から関東鉄道筑波山口行きバスで50分、筑波山口乗換え、筑波山神社入口行きバス10分 - 駐車場
- 駐車場 あり
- 営業時間
- 境内自由
- 連絡先
- 電話番号: 029-866-0502
- 公式サイト
- キーワード
マップ
詳細情報
筑波山神社は、茨城県つくば市の霊峰・筑波山を御神体として仰ぐ古社です。創建は三千年以上前とも伝えられ、関東有数の歴史を誇る神社として知られています。筑波山は標高877メートルの双峰の山で、西峰に筑波男大神(つくばのおおかみ/伊弉諾尊)、東峰に筑波女大神(つくばめのおおかみ/伊弉冉尊)を祀り、男女二神の夫婦神として古くから信仰を集めてきました。中腹にある拝殿は両峰を遥拝するための場所として建立され、山頂を含む約370ヘクタールの広大な境内を有しています。山頂からは関東平野を一望することができ、その眺望の美しさは古来より人々を魅了してきました。
信仰とご神徳
筑波山神社は、伊弉諾尊と伊弉冉尊の夫婦神を祀ることから、縁結び・夫婦和合・家内安全のご利益で広く知られています。古来より「筑波嶺(つくばね)」は男女の契りを象徴する山として『万葉集』にも詠まれ、恋愛や結婚の成就を願う人々の参拝が絶えません。また、交通安全、厄除け、商売繁盛などの祈祷も行われており、年間を通して多くの参拝者が訪れます。神前結婚式も人気があり、自然と歴史に包まれた神聖な雰囲気の中で挙式が行われます。
歴史
筑波山の信仰は、古代に人々が山や自然を神と崇めた時代にさかのぼります。その美しい双峰の姿から男女二神が祀られるようになったと伝えられています。『常陸国風土記』や『日本書紀』にもその名が見られ、第十代崇神天皇(約二千年前)の時代には、物部氏の一族である筑波命が筑波国造に任じられ、以来、筑波氏が祭政一致のもと神社を奉仕したと伝わります。
第十二代景行天皇の皇子・日本武尊(やまとたけるのみこと)が東征の帰途に登山したという伝承も残り、その際の御歌に由来して「連歌岳(れんがだけ/蓮花岳)」の名が付いたといわれています。奈良時代には『万葉集』に筑波山を詠んだ歌が二十五首も収録され、常陸国を代表する霊峰として広く親しまれました。平安時代の『延喜式神名帳』(927年)には、男神を祀る「筑波男ノ神社」が名神大社、女神を祀る「筑波女ノ神社」が小社として記載されており、現在の筑波山神社はこの二社を合わせ祀る形を継承しています。
中世に入ると仏教の興隆により、筑波山には堂塔が建ち並び、神仏習合の聖地として栄えました。鎌倉時代には小田城主・八田知家の末子である八郎為氏が社務を司り、社の維持に尽力しました。江戸時代に入ると、徳川家康は江戸の北東(鬼門)を護る霊山として筑波山を崇敬し、祈願所を設けました。以後、歴代将軍から篤い信仰を受け、幕府より神領1,500石が寄進されました。徳川家光の寄進による太刀(刀工・吉宗作)は国指定重要文化財に指定されています。
幕末には、藤田小四郎らによる尊王攘夷運動「筑波山挙兵」の舞台となりました。明治維新後、神仏分離令によって仏教建造物の多くが失われましたが、筑波山神社は神社として存続し、明治6年(1873年)に県社に列しました。
境内と建築
筑波山神社の拝殿は中腹の宮脇地区にあり、そこから男体山・女体山の両峰を遥拝します。境内には多くの摂社・末社があり、それぞれに歴史的・芸術的価値を有しています。
• 神橋(しんきょう)
切妻造の屋根を持つ美しい太鼓橋で、春(4月1日)と秋(11月1日)の御座替祭(おざがわりさい)の際にのみ渡ることが許されています。令和元年には約2年をかけた修復が完了しました。
• 日枝神社・春日神社
一つの拝殿を共有し、東西それぞれに祀られています。日枝神社の本殿には「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿の彫刻が施されており、その制作年代は日光東照宮のものより古いと伝えられています。
• 厳島神社
境内の池に浮かぶように建つ社殿で、鮮やかな彫刻や意匠の美しさが際立ちます。
朱塗りの拝殿や石段、杉木立に囲まれた参道など、江戸時代の社殿が多く残る境内は厳粛で荘厳な雰囲気を漂わせています。
年中行事と文化
筑波山神社の代表的な祭りは、春と秋に行われる「御座替祭(おざがわりさい)」です。
これは男女二神が季節ごとに座を替えられるという古式ゆかしい神事で、春(4月1日)と秋(11月1日)に執り行われます。五穀豊穣・夫婦和合を祈る祭りとして古くから伝わり、現在も多くの参拝者が訪れます。
また、筑波山名物「ガマの油売り口上」にちなむガマまつりも行われ、芸能奉納や露店が立ち並ぶ賑やかな行事として親しまれています。このほか、厄除け大祈祷祭や新春祭など、四季を通してさまざまな祭事が行われています。
現在の筑波山神社
現在の筑波山神社は、筑波山全体を神域とする自然信仰の中心地であり、同時に観光や登山の拠点としても多くの人々に親しまれています。ケーブルカーやロープウェイで容易にアクセスでき、拝殿からは関東平野を一望する絶景を楽しむことができます。
春の桜、夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色と、四季折々に異なる美しさを見せる筑波山は、古代から現代まで人々の心を惹きつけ続けています。筑波山神社は、自然と信仰、歴史と文化が一体となった関東屈指の霊験あらたかな名社です。
筑波山神社は、三千年に及ぶ歴史と伝承を持ち、神話・文化・自然美が調和した日本を代表する古社です。夫婦神を祀ることから縁結びや家内安全のご利益が篤く、徳川将軍家の崇敬を受けた格式高い社としても知られています。古代の歌に詠まれ、江戸の文化を映し、現代にもその姿を伝える筑波山神社は、まさに日本の信仰と自然の象徴といえる存在です。
【筑波山神社】関連動画
茨城県の観光スポット
茨城県の観光スポット一覧を見るアクアワールド茨城県大洗水族館
アクアワールド茨城県大洗水族館は、日本一のサメ飼育種類数を誇り、約580種68,000点の海の生物が展示される巨大水族館です。見どころは「イルカ・アシカオーシャンライブ」で、...
JAXA 筑波宇宙センター
JAXA筑波宇宙センターは、1972年に開設された日本最大級の宇宙開発拠点です。広大な敷地には、人工衛星やロケットなどの研究開発・試験施設、国際宇宙ステーション(ISS)「きぼ...