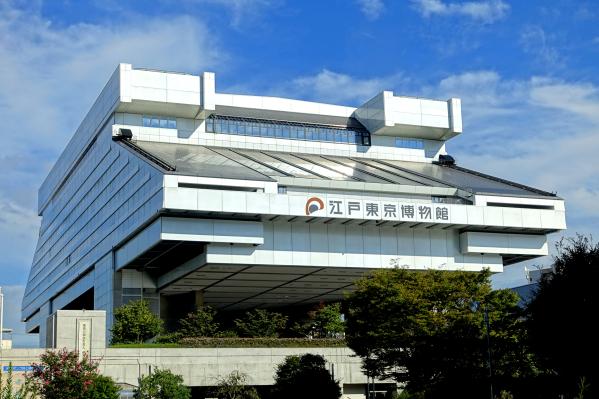神田神社(神田明神)|観光の魅力・歴史・アクセス方法・営業時間を写真&動画でチェック!
基本情報
- 名称
- 神田神社(神田明神) (かんだじんじゃ(かんだみょうじん))
- 所在地
- 101-0021 東京都千代田区外神田2丁目16-2
- アクセス
- JR総武・中央線 東京メトロ丸の内線「御茶ノ水駅」聖橋口より徒歩5分
JR東日本・東京メトロ・首都圏新都市鉄道「秋葉原駅」電気街口より徒歩7分
東京メトロ「末広町駅」より徒歩5分 - 駐車場
- 駐車場 あり
- 営業時間
- 境内自由(資料館は10:00~16:00<閉館>、祈祷は9:00~16:00、お守り授与は9:00~19:00)
- 定休日
- 年中無休
- 料金
- 無料 ※祈祷有料
- 連絡先
- 電話番号:03-3254-0753
- 公式サイト
- キーワード
マップ
詳細情報
神田神社(通称:神田明神)は、東京都千代田区外神田に鎮座する、東京を代表する歴史と格式を誇る神社です。創建は奈良時代の天平2年(730年)とされ、1300年近い歴史を持ちます。古くから神田、日本橋、秋葉原、大手町、丸の内、豊洲市場、旧神田市場を含む108の町会の総氏神として、人々の厚い信仰を集めてきました。「明神さま」の愛称で親しまれ、商売繁盛・縁結び・除災厄除といったご利益を求めて、年間を通じて多くの参拝者が訪れています。
ご祭神とご神徳
神田神社には、以下の三柱の神様が祀られています。
大己貴命(おおなむちのみこと)──だいこく様
一般に「だいこく様」として親しまれる神で、大国主命(おおくにぬしのみこと)と同一視されることが多く、出雲大社の御祭神としても有名です。国土経営、医薬、殖産、夫婦和合、縁結びの神様として広く信仰されるほか、幽冥(かくりよ)すなわち祖霊の世界を守護する神としても、人々の暮らしや心の安寧に深く関わる存在です。
少彦名命(すくなひこなのみこと)──商いと健康の神
少彦名命は、商売繁盛、医薬健康、開運招福のご利益で知られる神様です。高皇産霊神の御子神であり、大己貴命と共に国づくりを成し遂げたとされています。小さな身体ながら大きな智慧を持ち、「えびす様」と習合されることもあり、商いの神様として多くの商人に信仰されています。
平将門命(たいらのまさかどのみこと)──まさかど様
平将門公は、平安時代中期に承平・天慶の乱で関東の独立を図り、民衆のための政治改革を志した武将です。延慶2年(1309年)に神田神社に合祀され、以後は除災厄除の神様として崇められるようになりました。御首(みしるし)は現在も千代田区大手町の「将門塚」に祀られています。
歴史
神田神社の創建は天平2年(730年)、出雲系氏族である真神田臣(まかんだおみ)によって、武蔵国豊島郡芝崎村(現在の千代田区大手町・将門塚周辺)に建立されたと伝わります。鎌倉時代には、天変地異の鎮静を願って平将門公を祀り、時代とともに信仰の中心としての役割を深めていきました。
江戸時代初期の慶長5年(1600年)、徳川家康が関ヶ原の戦いに際し、神田神社に戦勝祈願を行いました。戦いは神田祭の日に勝利に終わり、これにより神田神社は「江戸総鎮守」として徳川将軍家の篤い崇敬を受けるようになりました。元和2年(1616年)には、江戸城の表鬼門(北東)を守る現在の外神田の地に遷座され、幕府によって社殿が整備されました。
明治時代に入ると、社名は正式に「神田神社」と定められ、「東京府社」「准勅祭社」に列せられました。明治天皇も明治7年(1874年)に御親拝され、皇室からの信仰も受ける存在となります。なお、「神田明神」という呼称は今もなお通称として広く親しまれています。
大正12年(1923年)の関東大震災では社殿が焼失しますが、昭和9年(1934年)には鉄骨鉄筋コンクリート造、朱塗りの社殿として再建されました。この社殿は東京大空襲の際にも奇跡的に焼失を免れ、昭和・平成の復興とともに地域の希望の象徴となりました。
戦後は、隨神門や明神会館、文化交流施設「EDOCCO」などが整備され、伝統と現代が調和する神社として発展を続けています。
神田祭と現代の神田神社
神田神社で最も有名な行事が、「神田祭」です。江戸時代から続くこの祭礼は、山王祭・深川八幡祭と並んで江戸三大祭の一つに数えられています。江戸時代には山王祭と隔年で交互に斎行されていました。現在では奇数年の5月に大規模に開催され、神輿が都心を巡行する様子は壮観で、東京の街全体が祝祭ムードに包まれます。
また、秋葉原に近い立地を活かし、IT関連企業やエンジニアによる安全祈願が行われるほか、「ITお守り」など現代的な授与品も人気を博しています。さらに、アニメやゲームとのコラボレーションによるイベントなども開催されており、若者や外国人観光客の関心も年々高まっています。
神田神社は、1300年近くにわたり東京の中心で人々を見守り続けてきた、まさに東京の「総鎮守」です。伝統的な信仰を大切にしながらも、現代の文化や社会のニーズに柔軟に対応するその姿は、多くの人々にとって魅力的な存在です。
【神田神社(神田明神)】関連動画
東京都の観光スポット
東京都の観光スポット一覧を見る渋谷スクランブル交差点
渋谷スクランブル交差点は、東京を象徴する名所の一つで、ピーク時には一度に1,000人以上が一斉に横断するとされています。渋谷駅からセンター街方面へ渡るこの交差点は、日常と...


![[4K]🇯🇵 神田明神 アニソン盆踊り おジャ魔女カーニバル!! 2025 / Bon dance at Ojamajo Carnival!! in Kanda Myojin Shrine.](https://i.ytimg.com/vi/udzVht-ykLs/mqdefault.jpg)