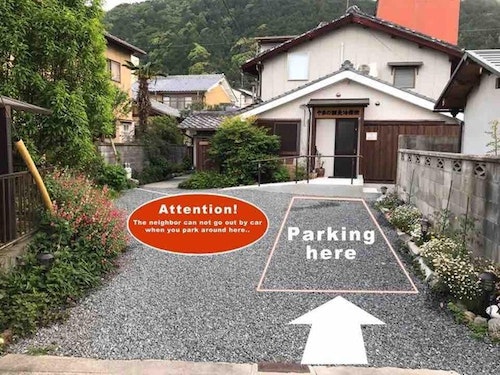天龍寺|観光の魅力・歴史・アクセス方法・営業時間を写真&動画でチェック!
天龍寺の建築にかかる費用は、元(当時の中国)との貿易で得たとされ、その貿易船は「天龍寺船」と呼ばれました。数々の火災に見舞われながらも、その都度、復興しています。多くの伽藍は明治以降に建てられましたが、夢窓疎石が手がけた曹源池庭園は現存し、国の史跡・特別名勝にも指定されています。
庭園は四季折々の美しさがあり、特に春には多種多様の桜が咲き誇ります。これは後醍醐天皇が吉野の桜を愛したため、創建時に吉野から桜が移植されたとされています。
法堂の天井画には「雲龍図」があり、見る角度によって龍が目を向けているように見える「八方睨みの龍」が描かれています。北門からは竹林の道に繋がっており、嵐山散策の帰りに立ち寄るのもおすすめです。
天龍寺は歴史、文化、自然の美しさが一堂に会する場所であり、訪れる者に静寂と感動を与えてくれます。
基本情報
- 名称
- 天龍寺 (てんりゅうじ)
- 所在地
- 〒616-8385 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68
- アクセス
- 京福電鉄嵐山線「嵐山」駅下車前
JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」駅下車徒歩13分
阪急電車「嵐山」駅下車徒歩15分
バスでのお越しの方
市バス11、28、93番で「嵐山天龍寺前」下車前
京都バス61、72、83番で「京福嵐山駅前」下車前 - 駐車場
- あり 100台
- 営業時間
- 8時30分~17時 [受付終了16時50分](庭園受付・北門受付)
- 定休日
- なし ※法堂「雲龍図」特別公開は土曜日・日曜日・祝日のみ[春夏秋は毎日公開期間あり]
- 料金
- 庭園(曹源池・百花苑)
・高校生以上:500円
・小中学生 :300円
・未就学児 :無料
受付時に障害者手帳を提示された方は、本人および介護者1名まで100円引き
諸堂(大方丈・書院・多宝殿)
・庭園参拝料に300円追加
法堂「雲龍図」特別公開
・1人500円(上記通常参拝料とは別) - 連絡先
- 電話番号:075-881-1235
- 公式サイト
- キーワード
マップ
詳細情報
天龍寺は、京都市右京区嵯峨嵐山に位置する臨済宗天龍寺派の大本山で、世界文化遺産「古都京都の文化財」の一つにも登録されている名刹です。美しい自然と深い歴史に包まれた境内には、禅宗の教えと日本文化の粋が凝縮されており、訪れる人々に静寂と感動を与えてくれます。
天龍寺の創建と歴史
天龍寺は、1339年(暦応2年)、室町幕府の初代将軍・足利尊氏が、後醍醐天皇の冥福を祈るために建立しました。後醍醐天皇は、南北朝時代に南朝を開いた天皇としても知られています。開山(初代住持)には、高名な禅僧夢窓疎石(むそうそせき)が招かれました。
この地はもともと、嵯峨天皇の皇后である橘嘉智子(たちばなのかちこ)が開いた禅寺「檀林寺(だんりんじ)」の跡地であり、後には後嵯峨上皇の仙洞御所、亀山上皇の仮の御所も営まれた由緒ある場所でした。
寺の造営資金は、足利尊氏の弟・直義が夢窓疎石と相談のうえ、当時中断していた元(中国)との貿易を再開することで捻出されました。この貿易船は「天龍寺船」と呼ばれ、以後の日本の貿易史にも名を残しています。
完成は1345年(康永4年)で、創建当初から高い格式を持ち、京都五山の第一位として長く日本の禅宗の中心的役割を担いました。
度重なる災難と再建
天龍寺は、壮麗な伽藍と広大な寺域を有していましたが、創建以来、8度の大火災と戦乱に見舞われました。中でも、1447年(文安4年)と1468年(応仁2年)の火災や、応仁の乱による被害は甚大で、再建には長い年月を要しました。
1585年(天正13年)には、豊臣秀吉の援助によりようやく復興が始まりましたが、その後も火災や兵火に襲われます。特に1864年(元治元年)の「蛤御門の変」では、長州藩の陣営となったことで再び伽藍が全焼しました。
明治時代に入ると、再建が本格化し、法堂・大方丈・庫裏が明治32年(1899年)に完成。小方丈(書院)や多宝殿、茶席祥雲閣・甘雨亭なども順次再建され、昭和初期には現在の寺観がほぼ整いました。
曹源池庭園(そうげんちていえん)
天龍寺の見どころの一つが、開山・夢窓疎石によって作庭された曹源池庭園です。この庭園は、日本で最初に史跡および特別名勝に同時指定された庭園の一つであり、約700年前の姿を今に伝えています。
池泉回遊式のこの庭園は、嵐山や亀山を借景に取り入れ、自然石を用いた石組や三尊石、浮島、登龍門伝説に基づく「鯉魚石(りぎょせき)」など、細部に至るまで禅の精神と美意識が表現されています。
庭園は四季折々に姿を変え、春は枝垂桜、夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪景色と、一年を通して訪れる人々を魅了します。特に春の桜は、後醍醐天皇が吉野の桜を愛したことにちなみ、創建時に吉野から移植されたと伝えられています。
法堂と雲龍図
天龍寺の法堂(はっとう)は、説法や法要などが行われる中心的な建物です。天井には、日本画家加山又造によって描かれた巨大な「雲龍図(うんりゅうず)」があります。これは、開山650年遠諱(おんき)記念として制作されたもので、迫力と気迫に満ちた作品です。
この龍は「八方睨みの龍」と呼ばれ、どの角度から見ても目が合っているように感じられるのが特徴です。訪れた際はぜひ、角度を変えて鑑賞してみてください。
その他の見どころ
方丈には、藤原時代の「釈迦如来坐像」が安置されています。
多宝殿は、吉野朝の紫宸殿を模して再建された建物で、春には周囲に枝垂桜が咲き誇ります。
庫裏(くり)の正面玄関には、達磨大師を描いた「達磨図」の衝立が掲げられています。これは前管長・平田精耕老大師の筆によるもので、独特な表情が訪問者の目を引きます。
北門から出ると、風情ある竹林の小径へと続いており、嵐山散策の途中に立ち寄るにも最適なロケーションです。
現在の天龍寺は、かつての広大な敷地のおよそ10分の1(約3万坪)となっていますが、それでも多くの堂宇や塔頭寺院を有し、京都を代表する禅宗寺院としての風格を今もなお保ち続けています。
天龍寺は、禅の教え、歴史の重み、そして自然の美しさが調和する場所として、国内外から多くの参拝者・観光客を迎えています。京都を訪れる際にはぜひ、心を静めてその荘厳な空間を味わってみてください。


![天龍寺 〜 嵐山にある世界遺産の臨済宗の寺院。嵐山を借景にした曹源池庭園は四季折々で美しい景色が楽しめます[No.097]](https://i.ytimg.com/vi/8G5DAlaRTyk/mqdefault.jpg)

![天龍寺 〜 世界文化遺産。方丈から眺める曹源池庭園。嵐山を借景に美しい眺めをご覧ください[No.351]](https://i.ytimg.com/vi/-0_ftYfJ1aU/mqdefault.jpg)