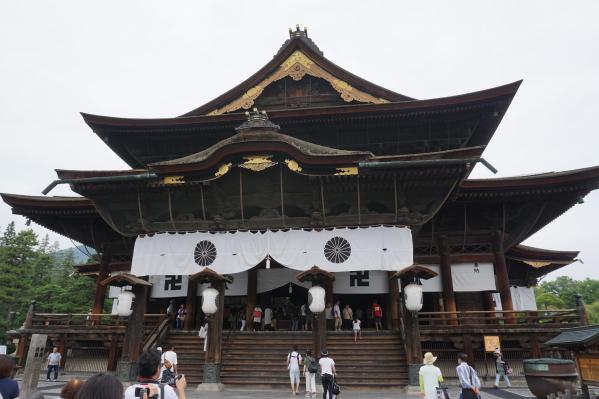松本城|観光の魅力・歴史・アクセス方法・営業時間を写真&動画でチェック!
松本城は美しい黒と白のコントラストが特徴で、城内からは壮麗な北アルプスや松本市街を一望できます。また、歴史的にも非常に価値が高く、小笠原氏が再入城した1582年には「松本城」と名前が変わり、城下町の整備も進みました。1590年には豊臣秀吉による天下統一と徳川家康の関東移封に伴い、石川数正が松本城に入城。その後、2代にわたって石川氏が大改修を行い、近世城郭の形となりました。
この城は松本の街のシンボルであり、何度もの存続の危機を市民の手によって乗り越えてきました。特に季節によって変わるその美しさは、多くの観光客を惹きつけます。また、連結複合式天守という珍しい構造を持っている点も見逃せません。
基本情報
- 名称
- 松本城 (まつもとじょう)
- 所在地
- 長野県松本市丸の内4-1
- アクセス
- 松本ICから 4km 15分
JR中央本線 松本駅下車 バス8分
JR中央本線 松本下車 徒歩15分 - 駐車場
- 普通車110台 大型車24台
- 営業時間
- 入園自由
- 料金
- 大人 700円 小・中学生 300円 小学生未満 無料
- 連絡先
- 電話番号:0263-32-2902
- 公式サイト
- キーワード
マップ
詳細情報
松本城の天守5棟が旧国宝保存法により国宝に指定されたのは昭和11年(1936年)のことで、昭和25年(1950年)には文化財保護法により重要文化財となり、昭和27年(1952年)に改めて国宝に指定され今日に至っています。わが国の重要文化財に指定されている城郭建築の中で国宝に指定されているのは、松本城、犬山城、彦根城、姫路城、松江城の5城のみです。
天守群の築造は二期に分かれ、建築・構造に違いがあります。中央の天守と北端の乾小天守、それを渡櫓で連結した3棟が文禄2年~3年(1593年~94年)にかけて石川数正、康長父子により築造されました。一方天守の南東に付設されている辰巳附櫓(たつみつけやぐら)と月見櫓は松平直政により寛永10年~15年(1633年~1638年)に築造されたものです。
現在天守の建物を残す城は12しかありません。そのうち五重の天守は松本城と姫路城だけです。五重天守の実物をみることができるのは2城だけです。
松本城の大きな特徴をあげてみます。
▶北アルプスを借景にした雄大な景色の中に立つ平城の天守
現存の12城の多くは平山城ですが、松本城は平城で、天守を囲んで三重の水堀が巡っています。バックに北アルプスの山々を借景として、堀に姿を写す天守は、他の城ではみられない絶景です。
▶黒と白の対比の美
天守建物は、壁面の上部を白漆喰、下部を黒漆塗りの下見板で覆っています。この漆喰の白と漆塗りの黒の対比が絶妙な美しさを醸し出しています。
▶戦闘に備えた天守と優雅な月見のための櫓
戦国末にあげられた天守に、世の中が落ち着いた寛永年代に増設された月見櫓がついています。月見櫓は舞良戸で三方を開放し朱塗りの刎高欄がまわりをめぐるという優雅なまったく武備がない建築物です。天守の建物に月見櫓が接続しているという造りは松本城だけで、時代によって天守の意味づけが変わってきた様子をみることができます。
▶外観は五重、内部は六階
外観は層塔型のように下から上に向かって細くなっていっていますが、内部には三階に屋根裏部屋のように外から見えない階ができています。これは乾小天守でも同様で、外観三重ですが内部は四階になっています。この外側から見えない階ができるのは、望楼型と呼ばれる天守に共通することで、松本城は、構造は望楼型でありながら、外見は層塔型のように見える天守になっています。
▶通柱によって高層化をはかる
一・二階を通柱で組み立て、その上に三・四階を通柱、五・六階を通柱で組んだものを積み上げていくという構造で、高層化をはかっています。松本城の通柱は天守三階でよくみることができます。
▶石垣内部に土台を支える柱16本
天守台のなかに、30~40センチメートルの直径で5メートルの材を16本たて、それを貫で繋ぎ、その上に天守の土台を敷いています。現代のパイル工法のような仕組みが施されています。
▶石垣下には筏地形
天守台南・西面の石垣を積むとき、地盤の弱いところの根石が沈みこまないために、筏のように材木を敷き詰め、その上に根石を敷いています。これによって、石垣の石を安定させています。
▶一階から三階までは、柱が林立
天守一階から三階までは柱の数が多く、四階から上は柱の数も減ってやや広い空間が設けられています。下層は骨組みがしっかり造られています。